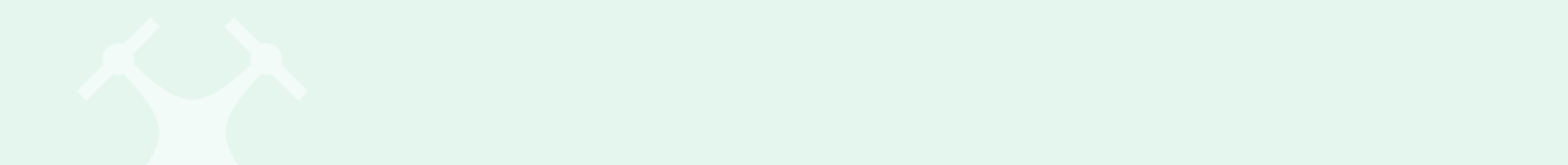【ホビーから軍事用まで】ドローンの種類一覧!形状別、用途別の特徴をご紹介

ドローンは近年、多くの分野で使用されるようになり、活用事例をニュースで耳にする機会も増えました。
機能は年々進化しており、10年前よりも格段に安定性と操縦のしやすさが向上しています。
業務においては無人化を促進する目的から今後更に普及が進むことが見込まれています。
一口にドローンと言っても、その用途は趣味で行う空撮から、業務で行うインフラ設備の点検、さらには軍事用の偵察や監視といった専門分野に至るまで多岐に渡ります。
どのようなドローンがあるのか13種類に分類し、用途別にまとめていきます。
また、ドローンの形状も大まかに分けて固定翼型・回転翼型・ハイブリッド型の3種類があり、それぞれの特徴も大きく異なります。
この記事ではドローンの用途別、形状別の特徴を紹介していきますので、ドローンに興味のある方は、自分の目的に合致したドローン探しにお役立てください。
形状別で見るドローンの種類一覧
ドローンと聞いて思い浮かぶのは4枚のプロペラを回転させて飛行するタイプのものではないでしょうか。
実は、ドローンには様々な形状があり、プロペラの数も3~8までと幅広くあります。
形状の違いによるドローンの分類は、以下の通りです。
・固定翼型
・回転翼型
・ハイブリッド型(eVTOL)
回転翼型はヘリコプターとマルチローターの2種類があります。
一般的なプロペラを回転させて飛行するドローンは回転翼型のマルチローターに該当します。
固定翼、回転翼にそれぞれに長所、短所があるので、ドローンの種類を一覧で解説していきます。
固定翼型
固定翼型は翼の形状が鳥の羽のような形をした機体を指します。
有人機の場合、旅客機や戦闘機などが該当し、無人機(ドローン)にも少数ですが固定翼型の機体があります。
固定翼型のドローンは回転翼型のドローンと比較して、
・飛行可能時間が長い
・飛行速度が速い
といった長所があります。
一方で、回転翼型と比較して以下のような短所もあります。
・垂直離着陸ができない
・飛行するためにある程度広い敷地が必要
・空中で一時停止することができないため、機敏な動作ができない
長時間飛行できるという点を活かして広範囲の測量を行う固定翼型ドローンが販売されています。
広大な敷地を飛行させる場合は固定翼型のドローンも選択肢として検討できます。
回転翼型
回転翼型は、プロペラを回転させて飛行する機体を指します。
回転翼型の機体は固定翼型と比較して、
・垂直離着陸機能により、狭い敷地でも離着陸ができる
・空中で一時停止ができる他、俊敏な動作が行える
という長所があります。
一方で、
・固定翼型と比較して飛行可能時間は短い
という短所もあります
機動性の高さと操作のしやすさから、多数の回転翼型の機体が開発されており、用途も様々です。
回転翼型のドローンには「ヘリコプター」と「マルチコプター」の2種類があり、それぞれの特徴について解説していきます。
ヘリコプター
ヘリコプターは頭上の大きなプロペラと、機体後部の小さなプロペラの2枚を回転させて飛行する機体です。
マルチコプターにはない、「可変ピッチ機構(プロペラの角度を変え、スピードを調整する機能)」がついている点が特徴です。
ヘリコプター型のドローンは、ラジコンヘリと呼ばれるホビー用機体の他、農薬散布に特化した産業用の機体が開発されています。
国内においてはヤマハ発動機の農薬散布ヘリコプターが長い歴史を誇ります。
マルチコプター
マルチコプターは「3つ以上」のプロペラを回転させて飛行する機体です。
ヘリコプターと比較して、可変ピッチ機構は無い一方、操作が容易であるため一般的に広く普及しています。
マルチコプター型のドローンは搭載されたプロペラの数によって名称が異なります。
●プロペラが3枚の「トライコプター」
●プロペラが4枚の「クアッドコプター」
●プロペラが6枚の「ヘキサコプター」
●プロペラが8枚の「オクトコプター」
プロペラの数が多い機体は風に流されにくく、安定性が高いという長所があります。
一方で、プロペラの数が多い=重量が重く、持ち運びづらいという短所もあります。
また、プロペラの枚数が多くなるほど、回転の際に発生する音も大きくなるため、周辺に住宅地がある場合などは騒音への理解を求める必要もあります。
プロペラの数による機体それぞれの特徴について解説していきます。
トライコプター
トライコプターは、3つのプロペラが搭載されたドローンです。
軽量で、後からパーツを取り付けやすいという利点がある一方、風に流されやすく、安定性に欠けるため、一般的に広く普及していない形状です。
クアッドコプター
クアッドコプターは、4枚のプロペラを持つドローンで、最も一般的なタイプの機体です。
・操作がしやすい
・安定した姿勢制御が可能
・ヘキサコプターやオクトコプターと比較して軽量で持ち運びやすい
・様々な機体が開発されており、入手しやすくバリエーションも豊富
という特徴があり、運用のしやすさから空撮や産業用途など、さまざまな分野で広く使用されています。
しかし、ローター(プロペラ)に一つでも不具合がある場合、機体の姿勢を維持することが難しくなるという欠点があります。
そのため、飛行前、飛行後に機体点検を毎回行い、故障や動作不良などの不具合がないか都度確認することが大事です。
ヘキサコプター
ヘキサコプターは、6枚のプロペラを持つドローンです。
前述のクアッドコプターよりも、故障に対する耐久性が高いという特長があります。
6つのローター(プロペラ)のうちの1つが故障した場合でも、残りの5つでバランスを保ちながら飛行を続けることが可能な機体もあります。
ただし、クアッドコプターよりも重く、持ち運びやすさにおいて難点があります。
クアッドコプターより数は少ないものの、ヘキサコプターも空撮や産業用途で広く利用されており、比較的メジャーな種類です。
オクトコプター
オクトコプターは、8つのプロペラを持つドローンです。
ヘキサコプター同様、1つのローター(プロペラ)が故障した場合でも、他のローターで飛行を続けることが可能な機体もあります。
マルチコプターの中で最も飛行の安定性に優れ、重い機材を搭載する能力があります。
一方で重量が重く、持ち運びづらいという難点があります。
重い機材を搭載できる点が重宝され、産業用ドローンとして空撮、高精度な測量、インフラの点検など多岐にわたって活用されています。
ハイブリッド型(eVTOL)
近年では、固定翼、回転翼が一体となった機体が開発されています。
これは固定翼の機体にプロペラが搭載された形状をしており、eVTOL(電動垂直離着陸機)という名称で呼ばれています。
eVTOLは【パワードリフト機】という名称で呼ばれることもあります。
有人機では「オスプレイ」などがeVTOLの代表格です。
固定翼、回転翼それぞれの長所を兼ね備えており、
・飛行可能時間が長い
・狭い敷地でも離着陸ができる
・空中で一時停止ができる他、俊敏な動作が可能
という特徴があります。
この特徴を活かして、長距離の物資運搬での活躍が期待されています。
用途別で見るドローンの種類一覧
ドローンは用途別にさまざまな種類が存在し、それぞれの目的に特化した機能や性能を備えています。
用途別に分類する場合、ホビー用と産業用の2種類に大きく分けることができます。
ホビー用は空撮など個人利用、産業用は点検や災害救助など法人の業務で利用される機種です。
一般的にホビー用は小型で安価、産業用は様々な機能が搭載されている分、大型で価格も高価という傾向があります。
ホビー用、産業用ともに様々な機種があり、活用できる分野も多岐に渡りますので、利用用途に応じて自分に合った機体を探してみましょう。
ホビー用ドローン
ホビー用ドローンは個人が趣味で利用することに特化したドローンです。
・室内で手軽に操縦練習ができる「トイドローン」
・撮影を行う「空撮用ドローン」
・ドローン競技で活躍する「競技用ドローン」
・ゴーグルにカメラ映像を映して操縦する「FPVドローン」
などホビー用途にも様々な種類の機体があります。
それぞれの特徴も大きく異なるので、ホビー用ドローンを分野別に紹介していきます。
トイドローン
トイドローンは、おもちゃのようなデザインが特徴の小型ドローンです。
明確な定義は存在しないものの、一般的には重量が100g未満の機体を指します。
サイズが小さく、軽量な機体が多数を占めます。
カメラ無しの機体から、高性能なカメラが搭載され、室内で空撮が楽しめるものまで多岐に渡ります。
また、専用のアプリをインストールしてスマートフォンで操作する機体もあります。
トイドローンは小型であるため、位置補正機能や障害物回避機能が搭載されていない機体がほとんどです。
基本的に室内で飛行することが前提の設計であるため、屋外で飛行した場合には風にさらわれて紛失したり周囲の物を損壊する危険性が高くなります。
小型で扱いやすく、空撮用ドローンと比較して安価であるため、初心者が操縦練習を始める際に適した機体と言えます。
空撮用ドローン
空撮用ドローンは、空からの撮影に特化した機能を多く有する機体です。
高性能カメラが内蔵されていることが多く、手ぶれ補正機能を備えている機種も多数あるため、特別な撮影技術が無くても空撮を手軽に楽しめる仕様になっています。
主に個人の趣味として利用されることが多いですが、映画製作やプロモーション映像の撮影においても広く利用されている姿が見受けられます。
テレビクラスの4K、映画クラスの8K撮影ができる機体やズーム機能を搭載した機体もあり、産業用と遜色ない性能を誇ります。
空撮用ドローンの価格帯は幅広く、3万円ほどで購入できるものから100万円以上のものなど、多岐に渡ります。
カメラの性能が高い、長時間飛行ができる機体ほど高価になる傾向があるため、これから空撮を始めたい方は撮影に必要なスペック(画質、飛行時間、重量など)を吟味し、適した価格のドローンを探しましょう。
屋外で機体を目視せずにカメラ映像を見ながら映像を撮影する場合、「目視外飛行」に該当し、航空局へ事前に飛行申請を行う必要がある点にも注意です。
競技用ドローン
競技用ドローンは、ドローン競技に使用される機体です。
速さを競うドローンレースの他に、ドローンを操縦してゴールを目指す「ドローンサッカー」などの競技もあります。
競技においては素早い動きが必要となるため、一般的なドローンよりも高速で飛行できる設計になっています。
また、パーツの変更が可能で自分で機体をカスタマイズできるという点も特徴です。
一般的なドローンに搭載されている衝突回避機能や高度維持機能などが無いため、高度な操縦技術が求められます。
加えてパーツが破損した場合には都度付け替える必要があるなど、耐久性の面でも難点がありますが、一般的なドローンにはできない高速かつダイナミックな動作ができるのが魅力です。
FPVドローン
FPVドローンとは、ファーストパーソンビュー(FPV)カメラを搭載したドローンで、一人称視点での映像をリアルタイムで楽しむことができます。
このカメラの映像は、専用のゴーグルやディスプレイ装置に送信され、ユーザーはドローンに搭乗しているかのような臨場感を味わえます。
FPVドローンは主にドローン競技や空撮に利用され、スピード感と迫力のあるフライト体験が魅力となっています。
注意しなければならない点は、FPVカメラは5GHz帯の電波を使用して映像を送受信するため、電波法の規制対象となります。
5GHz帯の電波を使用するためには、アマチュア無線技士などの資格取得や無線局の開局手続きが必須となり、FPVドローンの利用には事前準備が必要です。
産業用ドローン
産業用ドローンは、点検や物流、災害救助などの各種分野で利用される業務用のドローンです。
近年、人手不足を補うために、これまで人が行ってきた仕事をドローンに置き換える取り組みが注目されています。
人手不足解消の他、危険な場所での作業や人が立ち入りづらい場所での作業をドローンが行うことで、人の安全性を確保できるという側面もあります。
赤外線カメラや点検用のライトが搭載されるなど、従事する業務に特化した装備が付いているのが特徴で、ホビー用ドローンよりも高価な場合がほとんどです。
また、ホビー用ドローンはコントローラーで手動操縦をする機種が大半を占めますが、産業用ドローンはプログラムによって自律飛行できるモデルも多く販売されています。
産業用ドローンには主に以下の種類があります。
・建物などの点検に使用する「点検用ドローン」
・土地の測量に使用する「測量用ドローン」
・農薬散布などに使用する「農業用ドローン」
・巡回などに使用する「警備用ドローン」
・災害時に状況把握などを行う「災害救助用ドローン」
・物資運搬を行う「物流用ドローン」
・ドローンショーなどに使用される「イベント用ドローン」
・水場や水中などで活用する「水中用ドローン」
・敵の追尾や攻撃を行う「軍事用ドローン」
それぞれの活用事例なども交えて紹介します。
点検用ドローン
点検用ドローンは、主にインフラ設備や建物外観の点検に活用されるドローンです。
従来の点検作業は高所や危険な場所で行われることが多く、作業員の負担が大きいことに加えて、作業のための足場を組み立てることが必要で点検期間が長期にわたることが課題としてありました。
点検用ドローンは高画質カメラとズーム機能が搭載され、空中からヒビやボルトのゆるみなど、問題となる箇所を見つけることを容易とします。
また、太陽光パネルなどは赤外線カメラを使用することで、周囲との温度の違いによる劣化箇所の発見ができます。
また、点検が必要な箇所の確認もドローンで取得した画像データをAIで分析し、短時間で割り出すことが可能になり、点検にかかる時間はより短縮されています。
人の立ち入り・足場の組み立てが不要となったことで点検完了までに必要な時間を大幅に減らすことができます。
屋内点検ドローン
ドローン点検はこれまで屋外で行うことが前提でした。
これは、ドローンが空中で安定した姿勢制御を行うためには「GPS信号」の受信が必要という技術的な理由によります。
暗所で屋根などの遮蔽物がある空間はGPS信号が受信できず、ドローンの動作が安定しないため、ドローン点検には向かないという課題がありました。しかし、近年では遮蔽物がある環境でも安定した飛行ができる「Skydio X10」の登場により、屋内点検にもドローンの活用が進んでいます。
「Skydio X10」はGPS信号に頼らず、ビジョンセンサー(周囲の画像を解析するセンサー)により、ドローンが自らの位置を把握し、安定してその場に留まることができます。また、暗所ではサーチライトをドローンに搭載し、周囲を照らすことで点検が可能になります。
トンネルや橋梁下など、遮蔽物のある空間におけるインフラ点検で活躍が期待されています。
» Skydioシリーズの紹介ページはこちら
測量用ドローン
測量用ドローンは、地形の把握や出来形管理などに用いられるドローンです。
土地の地形確認といった測量の業務は、これまで地上から大人数の人員を動員して行ってきました。
それゆえ作業の期間も長期にわたってきましたが、この作業を空中から行うことで、地形確認に必要なデータの収集が容易になり、作業期間・人員共に減らすことが可能になりました。
近年では、国土交通省もIoT技術を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図る「i-Construction」という取り組みを推進しています。ドローンを使った測量もその一つで、今後測量の分野でドローンの活用が広まることが予想されています。
ドローン測量には「写真測量」と「レーザー測量」の2種類があり、それぞれの特徴をご紹介します。
写真測量
写真測量は、ドローンに搭載したカメラを使用し、地上に向けて重複した写真を複数撮影することで行われます。
これらの写真には、人工衛星から取得した位置情報や高度情報が結合され、地図や地形の3Dモデルが生成されます。
この方法は、コストが比較的安価であるため、外注の場合でも約100万円、自社で準備する場合でも同程度の費用で導入ができます。
しかし、上空と地面の間に樹木や建物などの障害物があると、正確な測量が困難になることがあります。
したがって、事前に撮影エリアの環境を検討することが重要です。
レーザー測量
レーザー測量は、ドローンに搭載したレーザー測距装置を用いて地上にレーザーを照射し、その反射を通じて地上との距離情報を取得する手法です。
この技術を利用することで、地形の3Dモデルや図面が高い精度で作成可能です。
特に、樹木などの障害物が存在しても影響を受けにくいという特徴があり、様々な環境で安定した測量が行えます。
しかし、導入コストは高く、外注の場合は約300万円、自社での準備には300万から1,000万円程度が必要です。
初めてドローン測量を導入する場合は、コストを抑えた写真測量用ドローンからスタートすることも一つの選択肢です。
農業用ドローン
農業用ドローンは、農薬散布や農作物の生育状況把握に用いられるドローンです。
広大な農地においては、農薬散布を人の手で行う場合、大きな負担がかかりました。
この農薬散布の作業をドローンに置き換えることで広大な敷地に農薬を散布でき、人にかかる負担を大幅に減らすことができるようになりました。また、ドローンを自立飛行させることで農薬を均一に散布することが可能となり、人の手で行うよりもムラのない散布が可能となりました。
農薬散布用のドローンにおいては、ヤマハ発動機のヘリコプター型ドローンが古くから用いられている他、マルチコプター型ドローンでは、世界的シェアを誇るメーカーDJIの「AGRAS」シリーズが有名です。
加えて、農作物の生育状況をカメラなどで解析し、虫食いの発生状況などを早期に発見することが可能になりました。
農業分野でもIoT技術を導入する「スマート農業」の取り組みが始まっており、今後も人手を減らすために機械の導入がますます進んでいくものと思われます。
警備用ドローン
警備用ドローンは、広範囲の監視を行うドローンです。
工場や大規模イベント会場を巡回し、空中からの監視を行うことができます。
センサーを使って不審者や不審物を検知したり、赤外線カメラで夜間の監視を実現しています。
自律飛行が可能なドローンは、事前に設定したルートを無人で飛行し、定期的な巡回を行うことにより警備の効率を向上させています。
さらに、AIを利用した自動検知システムにより不審者を発見した際には、現場に急行し、撮影や追跡を行う機能も搭載されています。
不審者発見の他、自殺が多発するエリアの巡回や、砂浜などで体調不良の人がいないか発見する取り組みも行われています。
農作物を栽培する地域においては、赤外線カメラによる夜間の巡視で害獣の発見なども行えます。
警備用ドローンの活躍は多岐に渡り、今後も広範囲の巡視において活用が広まると見込まれています。
災害救助用ドローン
災害救助用ドローンは、災害現場の状況把握や人命救助を行うドローンです。
人の立ち入りが難しい火災現場や土砂崩れの被害を上空から把握することができます。
消火剤を搭載し、火災現場の上空で消火剤を落下させることで無人で迅速に消化に取り掛かることもできます。
被害状況の把握のみでなく、人の捜索救助などにも活用でき、赤外線カメラを搭載した機体は、暗い場所での被災者捜索を可能にします。
また、投下機能を持つドローンは、救命浮き輪や医療品を必要な場所に届けることができます。
これにより、迅速かつ的確な判断が行え、救助活動の効率を向上させます。
地震をはじめとした災害が多発する今、災害に迅速に対処できるドローンの存在は、ますます重要性を増しています。
物流用ドローン
物流用ドローンは、荷物を無人で配送するドローンです。
山間部や離島、災害現場への物資の配達は、配達の手間や立ち入りの難しさから必要な物資がすぐに届けられないという課題がありました。
この立ち入りが難しい場所への配達をドローンに置き換えることにより、短時間に迅速で配達ができるようになりました。
既に離島や山間部においてはドローンによる配達の取り組みが行われていますが、今後都市部でもドローン配達が活発になることが期待されています。
物流分野での人手不足に加え、2024年からトラックドライバーの労働時間規制が適用される「2024年問題」により、更に物流が遅れることが懸念されています。
ドローンによる配送は道路の交通渋滞などの物理的な規制を受けないため、車よりも早く目的地に到着できるというメリットがあります。
しかし、積載可能な重量は車と比べると少ないため、「何往復で必要な物資を全て運べるか、そのためにバッテリーは何本必要か」という効率を考えた輸送計画を立てる必要があります。
ただし、実用化に向けては安全性の確保が課題です。
操縦者にはドローンが落下した際に被害を少なくするために、極力人の少ないルートを選ぶほか、機体にパラシュートを搭載するなどの対策が求められます。
安全管理や飛行ルートなどの法整備は現在、官民共同での取り組みが進められており、都市部においても飛行がしやすい法改正が行われることに機体が寄せられています。
イベント用ドローン
イベント用ドローンは、各種イベントで活用されるドローンです。
イベントでの活用方法は多岐にわたり、ドローンショーやFPV(First Person View)を利用したライブ配信、さらにはドローン体験イベントなどがあります。
特に有名な2020年の東京オリンピックでは、開会式においてLEDライトを搭載した1,800台以上のドローンが光のショーを演出し、多くの人々に感動を与えました。
映像演出にはプロジェクターやLEDを搭載したドローンが必要であり、一方でリアルタイム配信にはFPVドローンが適しています。
ただし、夜間の飛行や人口集中地区上空での飛行には特別な許可が必要となるため、イベント業者はこれらの規制を考慮しながら多様な演出アイディアを検討しています。
軍事用ドローン
軍事用ドローンは、敵地への攻撃や偵察を無人で行うドローンです。
近年では、ロシアとウクライナの戦闘においてドローンが多用されているという報道で注目を集めました。
これらのドローンは、有人機と違って操縦者が危険にさらされることなく、高速かつ長時間の飛行が可能です。
その機能は多岐にわたり、高性能のレーダーやカメラを活用し、敵地域の監視や偵察が行われ、情報がリアルタイムで送信されます。また、AIを搭載した機体では、長時間にわたって敵を追尾することが可能です。
さらに、武装ドローンは爆弾を搭載し攻撃を行ったり、自爆ドローンとして敵に突撃したりすることもあります。
米軍は軍事用ドローンを積極的に活用し、日本でも自衛隊がドローン技術の導入を進めています。
ミサイルと違い、低コストで攻撃手段を確保できることから、注目を集めている兵器です。
防衛戦略においてその重要性が増しています。
水中ドローン
水中ドローンは水辺での活動において用いられるドローンです。
水中潜航が可能な小型無人潜水機で、遠隔操作で水中の撮影や作業が行えます。
狭い場所や深い水中での作業にも対応でき、2025年に発生した八潮市の道路陥没事故においては水道管の中の状況を水中ドローンで把握する作業が行われました。水中での通信は電波が届きにくいため、無線よりも有線タイプが一般的です。
水中ドローンは、カメラとLEDライトを搭載しているため、環境調査や、生物の観察が可能です。
さらに、給餌機能を持つ機体もあり、魚を誘導し漁業や釣りに役立てることもできます。
オプションのロボットアームによって物体の運搬や水質調査など、多様な作業が可能となります。
点検などと同じく、水中での人の活動には危険が伴うため、政府も水中ドローンの利用を促しており、今後の展開が期待されています。
ドローンを飛行させる際の各種注意事項
ドローンの利用が広がる中で、操縦資格や免許に関する法律や要件も整備されてきました。
特に、無人航空機を安全に扱うためには、必要な法制度を事前に理解しておくことが求められます。
各地域や国によって法律が異なるため、利用する場所の規制をよく調べることが重要です。
重量における規制
重さが100g以上のドローンを屋外で使用する場合、機体の情報を航空局のシステムに登録することが義務付けられています。
機体の情報を登録せずに飛行させると航空法違反となるため、新しい機体を購入したら飛行前に必ず機体登録を行いましょう。
» 登録方法はこちらのコラムを参照してください。
各種法律における規制
ドローンは、法規制により飛行ができない場合があります。
「航空法」という法律では、以下のようにドローンの飛行に対して規制があります。
≪規制対象となる飛行の空域 ≫
・空港等の周辺の空域
・高度150メートル以上の空域
・人口集中地区
≪規制対象となる飛行の方法≫
・目視外飛行
・夜間飛行
・人または物件からの距離が30m未満の飛行
・催し場所上空における飛行
・物件投下
・危険物輸送
上記の規制に該当する場合、航空局へ事前に飛行申請を提出し、許可・承認を得なければなりません。
屋外で機体を目視せずにカメラ映像を見ながら映像を撮影する場合、「目視外飛行」に該当するため、航空局へ事前に飛行申請を行う必要がある点にも注意です。
航空法以外にもドローンの飛行を制限する法律がありますので、» 各種法規制はこちらのコラムを参照してください。
国家資格が役立つ場面
国家資格を取得することにより、広範囲での飛行が可能になったり、飛行申請が必要な飛行が一部申請なしで飛行できるようになります。
第三者上空における特定飛行を行う場合、一等無人航空機操縦士の資格が必須となります。※1
これは広範囲で飛行を行う場合、特に物流分野においてドローンを活用する際に必要な資格です。
また、二等無人航空機操縦士の資格を取得することで通常は飛行申請が必要な
・目視外飛行
・夜間飛行
・人口集中地区における飛行
・人または物件からの距離が30m未満の飛行
上記が申請なしで飛行ができるようになります。※2
業務内容によって、資格取得が役立つ場面があるため、国家資格取得のための講習を受講するとよいでしょう。
※1 資格の他、第一種機体認証を取得した機体を使用し、その他法令に従う必要があります。
※2 資格の他、第二種機体認証を取得した機体を使用し、その他法令に従う必要があります。
世界における主要なドローンメーカー
ドローン市場は世界規模に及び、世界各国から多種多様な製品が登場しています。
主要メーカーであるDJIは中国のメーカーで、ドローンの世界シェアの7割以上を占めています。
特に映像品質の高さと使いやすさが際立っており、「Mavicシリーズ」や「Phantomシリーズ」などが代表モデルとしてホビー用から産業用まで幅広いユーザーから多くの支持を集めています。
また、近年ではアメリカ製ドローンの「Skydio」シリーズもDJIに負けない性能と屋内飛行の安定性により、点検や測量の分野で注目を集めています。
一方で、ACSLなどの国内メーカーも存在感を示しています。
安全保障への懸念から、海外製ではなく国産のドローンを使用したいという官公庁からのニーズに対応した機体を製造しています。
価格比較で見るドローンの選び方
ドローンを選ぶ際、まずは価格を見る方が多いと思われます。
市場には幅広い価格帯の製品が揃っており、それぞれのドローンが持つ機能や性能により価格が大きく異なります。
ホビー用、産業機ともに購入後のサポート体制やアフターサービスの充実度も重要なポイントです。
保証期間、修理への対応速度も購入時に確認しておきましょう。
価格や機能に注目するだけでなく、自分自身の利用目的や必要な性能をしっかり理解した上で選ぶことが、満足度の高い購入につながります。
複数のモデルを比較し、それぞれの特性を見極め、自分に最適なドローンを選びましょう。
価格帯は主に
・数千~3万円程度の低価格帯
・数万~十数万円程度の中価格帯
・数十万~数百万円程度の高価格帯の3つに分けられます
それぞれに該当するドローンと大まかな特徴を紹介いたします。
低価格帯:数千~3万円程度
該当するドローン:トイドローン
特徴:
・手ごろな価格でドローンを始めたい場合におすすめ
・センサーは基本搭載されておらず、フラフラとした動作をするため操縦練習向き
・風に弱く、数分程度しか飛行できないため屋外での飛行には不向き
・初期不良以外では交換・修理に対応していない場合が多い
中価格帯:数万~十数万円程度
該当するドローン:空撮用ドローン、競技(レース)用ドローン
特徴:
《空撮用ドローン》
・カメラは高画質である程度の風に耐えられる設計になっている。
・本格的な空撮を始めるなら5万円以上のドローンがおすすめ。
・映画などの本格的な映像撮影には数十万円の機体が必要な場合もある。
《レース用ドローン》
・高速移動ができ、パーツが自分でカスタマイズできる。
・基本セットは数万~十数万だが、パーツが破損したら都度付け替えの必要があるため、維持費がかかる。
高価格帯:数十万~数百万円程度
該当するドローン:産業用ドローン全般
特徴:
・中価格帯の機体よりも長時間飛行ができ、風に強い機体が多い
・それぞれの業務に特化した機能が搭載されている
・機体によってはカメラを付け替えたり、ライトやスピーカーを後付けできるものもある
産業機には1,000万円以上の価格の機体もあります、高価であるため、業務に必要な機能を満たす機体を慎重に検討しましょう。
まとめ:用途に応じたドローンの選択を
ドローン市場は技術の進歩とともに日々拡大しています。
最新機種の多くは、より正確な飛行制御や高精度な撮影を可能にしており、選択肢も豊富です。
特に新しい技術に興味がある場合は、最新情報を収集し、自身の用途に合ったモデルを選ぶようにしましょう。
適切なドローンを選択することで、趣味から業務利用まで、より満足度の高い体験を得ることができるでしょう。
秋葉原ドローンスクールでは機体の機能紹介セミナーを行っています。
ホビー用から産業用まで、最新機種の性能を実機の飛行を交えて紹介しております。
セミナー情報は随時更新しておりますので、» 直近のセミナー開催情報はこちらをご覧ください。
この記事を書いた人

講師・ドローンパイロット
上野
筆者プロフィール
2021年7月に前部署より秋葉原ドローンスクールの部署へ、
その後2021年8月よりJUIDA公認講師して活動中。
インドアなので夏の日差しにも、冬の寒さにも弱い。
» 上野のプロフィールを見る