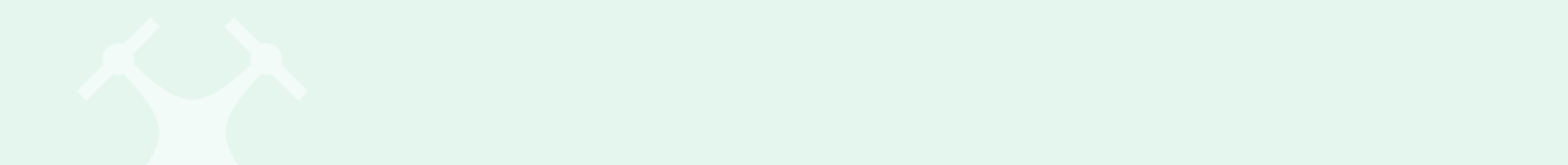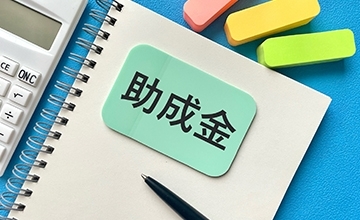【国家資格】ドローンの免許で何ができるのか。取得方法や仕事への可能性は?

近年、ドローンの利用が急速に増加していますが、それに伴いドローンの操縦に必要な資格についての関心も高まっています。
法人向けや個人の利用において、国家資格や民間資格の取得が推奨されています。
特に、国土交通省が2022年12月にスタートした国家資格制度は、飛行や操縦に関する安全性の向上を目指し設けられた基準です。
この制度により、利用者は新たなビジネスチャンスを得ることができるのです。
ドローン資格とは?
ドローン資格には主に国家資格と民間資格があります。
国家資格は、国土交通省が認定した資格であり、一定の基準に基づいて取得が求められます。
一方、JUIDAやDJIなどの民間資格は、さまざまな民間団体によって発行されており、その基準は団体によって異なります。
国家資格を取得することで、飛行や操縦の安全性を証明し、業務での活用がしやすくなる反面、民間資格は比較的安価で手軽に取得可能ですが、制約が多いと言えるでしょう。
国家資格と民間資格の違い
国家資格と民間資格の違いは、それぞれ認定する機関や法律的な効力、取得方法や利用範囲において大きな差があります。
国家資格は、一般的に国や地方自治体が認定する資格であり、法律に基づいて運用されています。
例えば、日本においては「ヘリコプター操縦士」や「看護師」などが該当します。
これらの資格を取得することにより、特定の職業を営むことが法的に保証され、一定の技術力や専門知識があることを証明できます。
一方で、民間資格は企業や団体が独自に設定した資格であり、法律による規定はありません。
日本でも多くの職業で民間資格が見受けられます。
例えば、ドローン関連の資格にはいくつかの民間団体が認定するライセンスがありますが、これらは国家資格に比べて取得が比較的容易で、必要性の判断も各人に委ねられています。
このように、国家資格は具体的な職業に必要不可欠なものであるのに対し、民間資格は自己啓発やスキルアップの手段として位置づけられることが多いです。
さらに国家資格は特定の業務を行うために必要とされることが多く、例えばドローンの国家資格の場合、特定の条件下での操縦において必要です。
これに対して民間資格は、特に業務なのか、趣味なのかを限定するわけではないため、より広範な用途で活用されることがあります。
したがって、自分のキャリアや目指す方向性に応じて、どちらの資格が適切かを慎重に判断することが重要です。
国家資格は法的な側面から見ても強固な基盤を持つため、特定の職業訓練や職務を希望する場合には必須となることが今後多くなることが見込まれます。
ドローンの飛行形態と4つのレベル分け
ドローンの飛行形態は、その運用レベルによって4つのカテゴリーに分けられます。
これにより運行する際の制約や責任も異なります。
まず、レベル1は「目視内での手動操縦飛行」です。
これは、操縦者がドローンを目の前で操縦し、基本的な操作ができることを示しています。
このレベルでは、飛行する地域が狭く、最初に習得すべき初歩的なスキルでもあります。
次に、レベル2は「目視内での自動/自立飛行」で、ドローンが設計されたプログラムに基づいて自動的に飛行する能力を示します。
操縦者は送信機やパソコンのアプリを使って設定を行い、その後ドローンは合図に従って自立して飛行します。
この技術は、特に測量や点検作業などでの使用が増加しています。
レベル3になると「無人地帯における(補助者なし)目視外飛行」です。
このレベルでは、操縦者自身が見えない(目視できない)場所までドローンを飛行する能力を指します。
ここでの無人地帯とは、山や海水域、河川、湖沼、森林など第三者の存在する可能性が低い場所です。
最後にレベル4は「有人地帯における(補助者なし)目視外飛行」です。
このレベルは最も高度なもので、ドローンが人がいる地域で安全に運行されるための高度な知識と技術が要求されます。
具体的には、リスク管理や緊急時の対処法、安全な飛行計画の立案が求められます。
一等資格と二等資格
一等資格と二等資格の主な違いは、操縦可能な飛行形態にあります。
一等資格を有する操縦士は、補助者なしで有人地帯での飛行が許可され、これにより、例えば空撮やインフラ点検などの業務で、効率よく広域をカバーすることができます。
一方、二等資格は補助者ありで無人地帯での飛行が原則とされており、規制があるため業務の範囲が限られています。
このため、二等資格は主に特定の環境下での使用に適しています。
一等、二等の基本を取得するとそれぞれの等級に応じて限定変更が可能となり、夜間飛行や目視外飛行、最大離陸重量25kg以上の無人航空機を飛行できる資格に限定解除をすることができます。
各資格に応じて求められるスキルや経験も異なります。
一等資格保持者は高度な操縦テクニックや緊急時の判断能力が求められ、独立して複雑な作業を遂行できることが期待されます。
一方、二等資格保持者は基本的な操縦スキルを持っていることが前提とされますが、補助者と連携して安全に操作する能力が重要になります。
したがって、業務内容や求められる操作レベルに応じた資格選択が重要であり、それぞれの資格の特徴をよく理解することが必要です。
各資格の特性を理解し、適切な資格を取得することが、ドローン操縦士としてのキャリアを築く第一歩となります。
飛行申請が不要なケースに!スムーズな運用事例
国家資格を持つことによって、特定の条件下で飛行申請が不要になるため、運用が非常にスムーズになります。
例えば、二等資格を取得していると、特定の飛行区域であれば申請なしでの運行が許可されます。
これにより、現場での作業が迅速に行えるようになる事例が各所で見受けられます。
特に建設現場や農業分野など、迅速なデータ収集や作業の効率化が求められる場面で、この資格の持つメリットは明確です。
申請手続きが省略される分、コストや時間の削減が見込まれ、現場の生産性向上にも寄与することができるのです。
ドローン操縦の信頼性向上|仕事や活用シーン
国家資格を持つことは、ドローン操縦士としての信頼性を大いに高めます。
資格保持者は、一定の学科と実技をクリアした上で資格を手に入れるため、技術的な裏付けがあります。
これにより、クライアントや取引先からの信用を得やすくなることが多いのが特徴です。
特にビジネスシーンにおいては、資格を持つことで新たな仕事のチャンスが増え、業界内での立場を強化することができます。
また、イベントやコンペティションなど、ドローンを使用した多様な活用シーンでも、資格を持つことで参加条件を満たすことが可能となり、個人の成長にも寄与します。
これらの点からも、国家資格の価値は非常に高いと考えられます。
ドローンの国家資格の取得方法
ドローンの国家資格を取得方法は、よく「自動車の免許証を取得する方法」に例えられることが多いです。
各都道府県にある“免許センター”に例えられるのが「指定試験機関」。
“教習所”に例えられるのが「登録講習機関」です。
ドローンの国家資格も自動車免許証の取得方法と同じように、教習所に例えられる「登録講習機関」を受講する場合がほとんどです。
取得の基本的な流れと手続き
ドローンの国家資格を取得するプロセスは、いくつかのステップを経ることで進められます。
登録講習機関を探し、受講申し込みを行います。
国土交通省が認可した登録講習機関では、国家資格のための教育プログラムが用意されており、講習内容は操縦技術だけでなく、法規や安全対策についての学科講習も含まれています。
多くの講習機関で実地訓練やシミュレーターを用いた授業を実施しており、受講者が実践的な技術を身につけることができるよう工夫されています。
登録講習機関では講習と一緒に実地試験も行っているため、試験に合格すれば指定試験機関での実地試験が免除されます。
次に、講習を修了した後は指定試験機関で試験を受ける段階に移ります。
試験は学科試験と身体検査に分かれており、両方の科目を合格する必要があります。
学科試験では登録講習機関で習った法令やヘリコプターや飛行機を含む無人航空機のシステム、安全な運航体制、運航上のリスク管理なども問われます。
身体検査はほとんどの場合、自動車の運転免許証を提示することで対応可能です。
主にドローンを目視する視力があるかなどが確認されます。
試験に合格すると、国家資格の交付申請を行います。
この際、必要な書類を揃え、提出することが求められます。
申請が許可されると、晴れてドローンの国家資格を取得することができます。
このように、ドローンの国家資格を取得するためには、登録講習機関での受講、試験合格、そして交付申請という一連の手続きが必要です。
各ステップを一つずつ丁寧に進めることが、資格取得への鍵です。
登録講習機関を活用するメリット
登録講習機関を利用する方法は、国家資格取得の際に多くの人に選ばれています。
これらの機関では、充実した講習プログラムが用意されており、初心者でも安心して学ぶことができます。
特に、実技と学科の両方を体系的に学べる環境が整えられているため、短期間で効果的に知識を深めることが可能です。
また、講習を修了することで、実地試験を免除される場合もあり、効率的に国家資格取得を実現することが期待されます。
受講生の評判や過去の合格実績を確認し、自分に合った機関を選ぶことが大切です。
指定試験機関を活用するメリット
指定試験機関で直接試験を受けて国家資格を取得する方法も選択肢の一つです。
このアプローチでは、学科試験と実技試験を一発で受験することになります。
費用も試験代のみとなるので、操縦技術や知識に自信を持つ人にとって、この方法は魅力的といえます。
実地試験は指定された全国の試験会場で行われ、規定に基づいた形式に則っています。
直接試験を受ける場合の費用や日程を事前に確認しておくことが大切です。
合格すれば国家資格を手に入れることができます。
ただし直接試験で不合格になってしまった場合、飛行試験のどこができているのかできていないのか、自分自身で試験結果を振り返って改善するしか方法がありません。
ドローン資格取得にかかる費用の相場
ドローン資格を取得する際の費用は、受講する講座や試験の形式によってさまざまです。
費用の相場は一般的に数万円から数十万円程度となることが多く、受講者のニーズや目指す資格によって異なります。
多くの受講者がこの費用をどうにか抑えたいと考えるため、情報収集がとても重要です。
予算に応じた計画を立てておくことで、スムーズに資格取得を進めることができるでしょう。
講習費用や試験費用の概要
ドローン資格を取得するためには、講習にかかる費用と試験にかかる費用が発生します。
登録講習機関での講習費用は各講習機関の選定やコースの種類によって異なります。
主に国家資格を受講する前に民間資格などをすでに取得している場合は「経験者」として判断され、民間資格など持っておらず、国家資格を受講する場合は「初学者」と分けられます。
「経験者」と「初学者」では学科、実地それぞれで必修の講習時間が大きく異なります。
一等の初学者と経験者とでは学科、実地講習合わせて68時間以上必要なところ、経験者では19時間以上と大きく差があります。
二等の初学者は学科と実地講習を合わせて20時間以上ですが、経験者だと6時間と短時間で取得を目指すことができます。
自ずと費用も講習時間に比例して数万円から数十万円の範囲内で変わってきます。
試験費用はほとんどの登録講習機関で講習費用に最低1回分は含まれています。
再試験になってしまった場合は別途必要で、再講習代、再試験代なども考慮する必要があります。
実地試験に合格した後は学科試験を受験します。
一等と二等とではそれぞれ試験代が異なり、一等が9,900円、二等が8,800円です。
身体検査で自動車の運転免許証で確認する場合は、5,200円必要となります。
これらの費用を事前に把握することで、より具体的な予算計画を立てることが可能です。
技能証明書の交付手数料額や登録免許税の納付額
ドローン資格取得にかかる総額を把握するためには、さらに無人航空機操縦者技能証明書の交付手数料も考慮しなければなりません。
交付手数料は一等、二等ともに3,000円です。
再交付、更新、限定変更の手数料は2,850円です。
ただし、一等のみ登録免許税として別途3,000円が必要です。
大きな金額ではないものの、例えば法人として従業員に国家資格を取得させるため社内稟議を通すには全体の費用を把握する必要があるかと思います。
費用を抑えるためのコツや選び方
費用を抑えるためのコツは、まず複数の登録講習機関の比較を行うことが重要です。
内容や費用の詳細を比較することで、最もコストパフォーマンスに優れた選択ができる可能性が高まります。
また、キャンペーンなどを利用することで、割引が適用される場合があります。
更に知人や他の受講者の口コミを参考にし、実績がある登録講習機関を選ぶことも重要です。
講習費用が安いところだけを注目してしまうと、「もっと飛行練習の時間が欲しかった」「自主練習の場所の確保が難しい」など料金だけでは決められない要素も非常に多いです。
卒業生の声など信頼性の高い講習機関であれば、その後の手間や費用が軽減できることにつながるでしょう。
初心者でも始めやすい学習法は?
初心者が学習を始める際には、学科なら市販の教材やカリキュラムを用いることも効果的です。
国家資格を目指すならば航空局のホームページに掲載されている「無人航空機の飛行の安全に関する教則」にすべて記載されています。
ただし初めて読むには難解な表現もあるかもしれないので、多くの講習機関では初心者向けの特別コースが用意されているため、これを活用することで基礎から学ぶことができます。
秋葉原ドローンスクールでも初心者向けのオリジナルコースを用意しており、一等を目指すための「トライアルコース」、二等を目指すための「ベーシックコース」がございます。
実技はとにかくドローンを飛ばすこと!おもちゃのトイドローンでもよいので、スマホで飛行できるドローンでなく、専用の送信機を使用して、スティックを動かして飛ばしてください。
おもちゃで手のひらサイズのドローンもあるので、部屋の中や室内の空きスペースなどで練習できます。
屋外は場合によっては飛行申請が必要になってしまう可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。
空調などの風をドローンにあてさせながらホバリング(一定の場所、高さでとどまり続けること)を繰り返し続ける。
慣れてきたら前後左右にドローンの機首の向きを変えてホバリングを続けるだけでも十分練習になります。
ドローンの基礎練習に広い空間は必ずしも必要ではないです。
ドローン資格で広がる仕事の可能性
近年、ドローン資格を取得することによって、新たな仕事の選択肢が広がっています。
資格を持つことは、特定の業務に必要不可欠なスキルと知識を証明するものです。
特に、ドローンを活用するビジネスが増加する中で、資格を有することで他者との差別化を図ることが可能です。
多様な業界で需要が高まっているため、資格を持つことは今後の就職や転職活動において大きなアドバンテージとなります。
映像や写真撮影
ドローン資格を取得することで、映像・写真撮影の分野においても新たなチャンスが生まれます。
特に、空撮技術は映画や広告、イベントの撮影において非常に需要が高く、「1つの映像作品の中でドローンが撮影したシーンを使っていない作品はない」というほど広く使用されています。
映像制作の現場では、ドローンの操作は高度な技術を必要とします。
撮影時に意図したアングルや構図にカメラを的確に捉えることができ、クライアントの期待に応える作品作りに貢献することが重要です。
これにより、映像制作会社や広告代理店などからのニーズが高まり、安定した仕事の獲得が期待できます。
農薬散布や測量、点検
農業分野においては、農薬散布の効率化が急務となっています。
ドローンを利用することで、広大な農地に対して均一に農薬を散布することができます。
資格を持つ操縦士は、これに対応するための専門知識を習得しており、安全かつ効果的に作業を行うことが可能です。
また、測量や点検作業に関してもニーズが高まっています。
特に、インフラ管理や建設プロジェクトにおけるデータ収集は、ドローンによって迅速かつ正確に行うことができます。
このような仕事は、資格を有する操縦士にとって非常に魅力的なものであり、最近では公共関係の業務を行う際は、国家資格の所有を仕様書の必要条件に定めている場合もあります。
開発・製造分野
ドローン資格は開発や製造分野でも活用されています。
ドローンを使用して工場の点検や設備の監視を行うケースが増えています。
資格を持つ操縦士がいてこそ、これらの作業を安全に効率良く実施できるため、企業からの需要が絶えません。
また、新たなドローン技術の開発に携わるためには、専門的な知識と技術が必要です。
ライセンス保持者は、ドローン関連の研究や開発、運用への参加が可能となり、将来的なキャリアの選択肢を広げることができるでしょう。
このように、ライセンスを取得することは多様な業務分野での活躍を促進します。
まとめ『ドローン資格で実現する未来』
ドローン資格は、急速に発展する業界への一歩を踏み出すための重要なステップです。
ドローン技術の利活用が広がり、多様な分野で新たな需要が生まれています。
特に、農業、物流、点検、そして映像制作など、さまざまな業務でドローンを活用するために、専門的な知識を持った操縦士の存在が求められています。
このため、資格を取得していることが仕事の幅を広げるポイントとなるのです。
また、国家資格は法令に基づいた安全かつ適切な運用を遵守する証明ともいえます。
従来の民間資格に比べ、国家資格はより高い信頼性を持ち、多くの企業からの支持を集めることが期待されます。
今後、ドローン操縦士の資格を持つことが、労働市場での競争力を高める要因となるでしょう。
おわりに『ドローン業界の成長と資格の必要性』
ドローン業界は、技術革新とともに急速に成長しています。
この成長に伴い、業務でドローンを使用する際の資格の必要性は一段と高まっています。
特に、2022年からの国家資格制度導入により、操縦士の技術や専門性がより重視されるようになり、安全な運用が期待されています。
業界ニーズに適応するためにも、資格を取得することが重要です。
多くの企業が、資格を持つ操縦士を優先的に採用する傾向があり、キャリアアップや安定した雇用を望むなら、資格取得は避けては通れません。
今後も拡大が見込まれるドローン市場で、資格を持つことで自己成長や新たな仕事の機会を創出することができるのです。
この記事を書いた人

講師・ドローンパイロット
井出
筆者プロフィール
2016年の秋葉原ドローンスクール開校前からドローンプロジェクトに参加
ドローンの講師をしながら、さまざまなメディアに出演
最近は腰痛が悩み
» 井出のプロフィールを見る