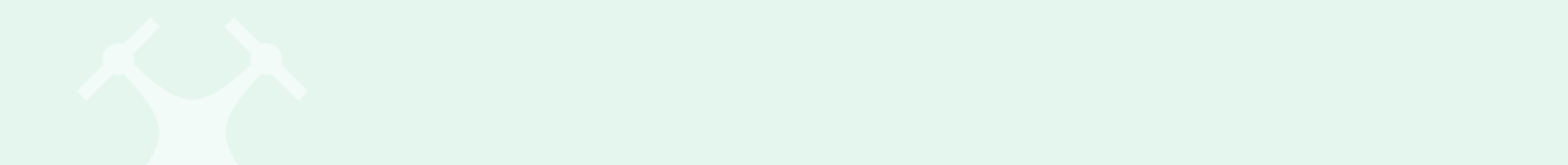【最新版】ドローンの法規制解説 | 飛行前に注意すべき5つの法規制

ドローンを使用する際には、法律や規制を理解し、適切に運用することが非常に重要です。
日本では、2015年の首相官邸へのドローンの墜落事件をきっかけにドローンに関する規制が強化されました。
また昨今では、ドローン関連事故の増加やプライバシー侵害の懸念により、最新のルールが随時更新されています。
飛行前に確認すべき重要なポイントのひとつは、ドローンを規制する法律への理解です。
これらの法律には、飛行可能な場所や高度、さらには登録や免許制度などが含まれており、守らなければならないルールが細かく定められています。
また、特定のエリア、たとえば人口密集地域や空港周辺では、事前に許可を取得する必要がある場合があります。
これらの規制違反は、罰則を招くだけでなく、他人に危害を与えるリスクも伴います。
さらに、ドローンを規制する法律では、機体のサイズや用途に応じて異なる義務が課されることがあり、購入前から飛行計画まで最新情報を確認することが欠かせません。
安全かつ合法にドローンを活用するためにも、自身の機体および使用目的に合致した法律やガイドラインを熟知し、それらに従うことを徹底しましょう。
このような準備が、より安全で快適なドローン体験の実現につながります。
日本のドローン規制とは
ドローンの運用については、法規制が厳格に定められています。
これにより、安全性や公共の利益が確保されることを目的としています。
今回は、主な5つの規制とその他規制についてわかりやすく一覧で解説するので、ドローンの使用を予定している方は自身の飛行計画が適法であるか確認しましょう。
1.飛行場所に関する規制
2.飛行方法に関する規制
3.機体重量に関する規制
4.電波に関する規制
5.プライバシーに関する規制
1.飛行場所に関する規制
ドローンを飛行できる場所は法律や条例で規定が定められています。
主に「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」の2つにより規制されており、その他にも「民法」や地方ごとの条例による規制があります。
これらの規制に違反しないよう、事前に規制対象となる場所で飛行しようとしていないか確認する必要があります。
「航空法」で規制された場所
航空法とは国土交通省が管轄する、ドローンを始めとした航空機の飛行に関してルールを定めた法律です。
この法律では以下の区域ではドローンの飛行が制限されています。
①150m以上の高さの上空
②空港周辺の空域
③人口集中地区(DID地区)の上空
④緊急用務空域(災害時に指定される災害現場上空)
これらはドローンの飛行によって、人や航空機に大きな被害を及ぼすことが想定される場所です。
原則として飛行は禁止されていますが、①~③は国土交通大臣に飛行申請を送り、許可が下りれば飛行可能となります。
④は一部の例外を除き、飛行申請を出しても許可は下りないため、飛行予定の場所が突発的に緊急用務空域に指定されていないか、事前に確認する必要があります。
住宅地などの市街地は多くの場所が③に該当します。
特に東京都内は半分以上が人口集中地区となりますので、飛行予定の場所が人口集中地区に該当する場合は事前に飛行申請を行う必要があります。
山や森林など、住宅地から離れた場所であれば人口集中地区に該当しないことがほとんどですが、事前に国土地理院の地図で飛行場所が人口集中地区に該当するか確認しましょう。
» 国土地理院地図はこちら
国土地理院の地図の使い方は» こちら(PDF)をご覧ください。
※参考:» 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
「小型無人機飛行禁止法」で規制された場所
小型無人機飛行禁止法は警察庁が管轄する法律です。
「重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空」におけるドローン(小型無人航空機等)の飛行を禁止しています。
重要施設というのは、以下のような施設です。
いずれも国の重要施設となっており、テロ等の危険を排除するため、ドローンの飛行は禁止されています。
・国会議事堂
・首相官邸
・危機管理行政機関
・最高裁判所庁舎
・皇居、御所
・政党事務所
・外国公館
・自衛隊施設・在日米軍施設
・成田国際空港、大阪国際空港など一部の空港
・原子力発電所
これらの施設の上空は、一部の例外を除いて飛行はできません。
対象施設上空だけでなく周辺の上空も含まれているため、該当する施設が飛行経路にないかマップ等で確認し、場合によっては飛行経路を変更する必要があります。
※参考:»警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」
「民法」で規制された場所
民法は私人間の日常の生活関係において一般的に適用される法律です。
ドローンの使用を直接規制していませんが、土地の所有権に関する規定があり、ドローンの飛行に関係しています。
ドローンに関連するのは主に民法207条で規定されている「土地所有権の範囲」という条項です。
この条項では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定めています。
私有地において無許可でドローンを飛行させた場合、土地所有権の侵害となります。
航空法や小型無人機飛行禁止法の規制に該当しない場所であっても、土地所有者の同意・承諾がない飛行は所有権の侵害となります。
そのため、所有者のわからない土地での飛行は控える必要があります。
「刑法」における規制
刑法は犯罪と刑罰に関する法律です。
民法と同様に、ドローンの使用を直接規制していませんが、ドローンの飛行に関係する条文があります。
例として、刑法第129条の内容に「過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する」とう記述があり、違反した場合は【過失往来危険罪】が適用されます。
ドローンで鉄道、新幹線、高速道路の車などに接近し、危険を生じさせた場合が該当します。
人が少ない地域の鉄道や車であっても刑法の対象外ですので、ドローンでこれらの乗り物に接近することは避けましょう。
その他、場所の規制をする法律
上記の他にもドローンの法律・条例で規制されているエリアとして、以下のような場所が挙げられます。
※()は法律の名称
・道路(道路交通法)
・河川(河川法)
・海岸(海岸法)
・港(港則法)
・船の航行の邪魔になる海上(海上交通安全法)
・公園(各地方自治体の条例)
・その他都道府県・市区町村の条例で禁止されている場所 など
その他都道府県・市区町村の条例で禁止されている場所は、例として東京などの都市でドローンを飛行する場合、東京都条例を確認する必要があります。
他の地域では問題なく飛行できた場所でも、違う地域では禁止されていたり許可が必要だったりするかもしれません。
ドローンを飛行させる場合は、必ず事前に飛行エリアの条例もチェックしておきましょう。
2.飛行方法に関する規制
「航空法」では飛行の方法についてもルールが定められています。
これは、飛行場所が規制に該当しない場合であっても遵守する必要があります。
飛行方法に関する規制は「禁止・遵守事項」と「承認が必要な飛行」の2種類から構成されるので、それぞれ解説します。
禁止・遵守事項(航空法)
ドローンを飛行させる際、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。
①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させない
②飛行前確認を行う
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させる
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない
①のアルコールは、アルコール入りのチョコレートも該当します。
②の飛行前確認は機体点検や飛行場所周囲の安全確認が該当します。
③に関しては、航空機(飛行機やヘリコプター等)はドローン(無人航空機)よりも航行が優先されるものですので、姿が見えたら速やかに航路を譲る必要があります。
④の他人に迷惑を及ぼす飛行は、速度を上げて急接近する場合などが該当します。
ドローンは自動車と同様、アルコールや薬物の影響下で飛行させると人や物に多大な影響を与えることが懸念されます。
特に航空機と接触事故を起こした場合、被害は計り知れません。
これらを遵守することは周囲の人、物だけでなく、今後のドローン業界の発展も守ることになります。
基本的なマナーとして、禁止・遵守事項は必ず守りましょう。
※参考:» 国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
承認が必要な飛行(航空法)
禁止・遵守事項と同じく禁止されているものの、承認が得られれば行える飛行方法があります。
①夜間飛行
②目視外飛行(肉眼で見えない範囲での飛行)
③人や物との距離が30m未満になる飛行
④お祭りやイベントなどの上空での飛行
⑤危険物の輸送(農薬散布など含む)
⑥物を投下すること(農薬散布など含む)
②の目視外飛行は、「操縦者から見えないくらい遠くまで飛ばす」ことの他に、「タブレットの映像など、ドローンのカメラ映像を見ながら操縦する」ことが該当します。そのため、ドローンで空撮を行う場合、ほとんどが目視外飛行となります。
①~⑥は飛行前に航空局に申請を送り、国土交通大臣から承認を得られれば飛行可能となります。
ただし国家資格を取得して一定条件を満たしていれば、①~③は飛行申請不要で飛行させることができます。
なお、飛行禁止場所を含めた航空法の規制は屋内の飛行においては対象外となります。
屋内で夜間飛行や目視外飛行を行う場合、申請は不要で飛行ができます。
ですが、人とドローンの距離が近い状態で行う飛行は怪我のリスクが高くなるため、安全管理には十分に注意しましょう。
※参考:» 国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
3.機体重量に関する規制
ドローンは機体重量によって、適用される法律が異なります。
また、重量が大きくなるにつれて法律の規制も厳しくなります。
なお、機体重量は「機体本体とバッテリーの重量の合計」を指します。
プロペラガードやペイロード(荷物や取り外し可能なカメラ)は重量に含まれません。
プロペラガードを付けない状態で99g、プロペラガードをつけた状態で105gであれば、99gの方が機体重量として適用されます。
機体重量によって規制が大きく変わるため、機体重量の定義もしっかりと覚えて、自分の機体は何グラム、何キロがあらかじめ確認しましょう。
今回は「100g以下のドローン」「100g以上25kg未満のドローン」「25kg以上のドローン」の3種類の規制について紹介します。
100g未満のドローン
重さが「100g未満のドローン」は、航空法における飛行場所の規制や飛行方法の規制の適用対象外となります。
従来は200g未満のドローンまで規制の対象外でしたが、2022年の法改正に伴い、対象となる重量が引き下げられました。
100g以下のドローンは「人口集中地区での飛行」や「目視外飛行」を行う場合でも航空局への事前申請なしで飛行が可能です。
また、100g以上のドローンに必要な「機体登録」も100g以下のドローンは不要となります。
ですが、あくまで航空法の適用対象外となるのみですので、小型無人機等飛行禁止法や民法など他の法律の対象となることに変わりはありません。
また、100g以下でも人や物に危害を加えた場合、損害賠償が発生する可能性がありますので、取り扱いには十分に注意しましょう。
100g以下のドローンの例:おもちゃのホビー用ドローンやマイクロドローン、ラジコン飛行機など
100g以上25kg未満のドローン
重量が100gを超えるドローンは航空法の規制対象となり、飛行場所や飛行方法が禁止事項に該当する場合は事前に申請を行う必要があります。
また、100g以上のドローンは航空局に使用者(操縦者)や機体の情報を登録する必要があります。
この機体登録を行わずに屋外でドローンを飛行させた場合、航空法違反となりますので機体登録は必ず行いましょう。
一般に販売されているドローンは100g以上25kg未満の重量に該当しますので、飛行申請や機体登録を行ったか、飛行前に確認しましょう。
機体登録の概要や登録方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
» コラム:『ドローンの機体登録 - 登録手続き方法について -』
25kg以上のドローン
25kg以上のドローンを屋外で飛行させる場合、必ず飛行申請を行わなければなりません。
25kg未満のドローンであれば場所の規制や飛行方法の規制に該当しなければ飛行申請は不要ですが、25kgを超えるドローンは規制に該当しなくても飛行申請が必要になります。
重さのある機体は墜落時に被害が大きくなる危険性が高いため、飛行申請が必須となります。
25kg以上の機体を飛行させる場合は、飛行前に必ず申請を行うと覚えましょう。
25kg以上の機体の例:農業用ドローン「AGRAS T30」
参考:» 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
4.電波に関する規制
ドローンの操縦やデータ通信は電波によって行われています。
そのため、日本の電波の取り扱いを定めた電波法も遵守する必要があります。
電波の使用には、通常であれば無線局の免許が必要となりますが、他の無線通信に妨害を与えない周波数であれば免許は不要で利用できます。
免許不要の要件として、「周波数2.4GHzで10mW以下」かつ「技適マークあり」の機器が該当し、スマートフォンなどもこの要件に該当するため、免許なしで使用ができます。
ドローンも「2.4GHzで10mW以下」かつ「技適マークあり」の要件に該当すれば免許なしで使用ができます。
大手メーカーが販売しているほとんどのドローンがこの要件に該当するので問題なく利用ができますが、一部に「5GHz以上」などの電波を使用して操縦するドローンがあり、この場合には免許が必要となります。
ドローン購入の際は、使用する電波の周波数が免許不要の要件に適合しているか、技適マークがついているかを確認するようにしましょう。
※参考:» 総務省「1.ドローン等に用いられる無線設備について」
5.プライバシー保護に関する規制
個人のプライバシー保護は、ドローン撮影を行う際に必ず考慮すべき重要な要素です。
ドローンによる撮影および撮影映像をインターネット上で公開することについての注意事項をまとめたガイドラインが総務省より公表されています。
ドローンは上空から広範囲の撮影ができるため、意図せず個人情報が映ってしまう可能性があります。
ガイドラインの内容を確認し、撮影前に注意すべき点を覚えましょう。
ドローンによる撮影映像等のガイドライン
ガイドラインでは、「撮影は撮影対象となる人物の同意を得ることが基本であり、無断での撮影は法律に反する行為」としてルールを厳格に定めています。
ドローンで撮影した写真・映像を、SNSやYouTubeなどで公開する場合、個人情報が映り込まないようにする必要があります。
写真・映像に「人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子、洗濯物など」が映っている場合、ぼかしを入れて個人情報が特定できないよう、加工をするなどの配慮が必要です。
写真・映像をインターネットに公開する場合、公開前に個人情報の映り込みがないか確認を行い、映り込みが見つかった場合は編集して個人が特定できないように加工しましょう。
※参考:» 総務省「ドローン」による撮影映像等の インターネット上での取扱いに係るガイドライン
まとめ:今後の規制の動向について
ここまで、ドローンに関する法規制を飛行時の注意点をまとめてきました。
規制が厳しい一方で、「有人地帯での目視外飛行【レベル4】」を可能にするため、ドローンの国家資格制度が定められました。
これにより、ドローンによる短時間配送や、山間部などアクセスの難しい地域への配達実現が期待されており、ドローンの利便性を高めるための法整備が進んでいることも確かです。
2025年以降にもドローンに関するルールが変わる可能性があるため、常に国土交通省 航空局のサイトを確認し、法律に関する最新情報をキャッチしましょう。
» 国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
この記事を書いた人

講師・ドローンパイロット
上野
筆者プロフィール
2021年7月に前部署より秋葉原ドローンスクールの部署へ、
その後2021年8月よりJUIDA公認講師して活動中。
インドアなので夏の日差しにも、冬の寒さにも弱い。
» 上野のプロフィールを見る